
『サキソフォン・コロッサス』はモダン・ジャズのバイブル的名盤、どのトラックを聴いても、“モダン・ジャズ”の圧倒的なパワーと魅力に溢れている。“モリタート”や“セント・トーマス”は、歌舞伎なら『勧進帳』、クラシック音楽なら『運命』同様、特にそのジャンルが好きでなくたって誰でも知ってるもんや…と思っていたけど、ジャズが、BGMとして“流れる”だけの時代になってからは、あながちそうでもないらしい… とはいえ、“サキコロなんかあんまり当たり前で耳にタコできて、もう聴く気もせんわ。”と言うジャズ通も多いのではないでしょうか?このセリフは、かつて私がミナミの中古レコード店に行くと、必ずハングアウトしていたネクタイ姿の常連さんの言葉です。
それほどベーシックな名盤なのに、今まで我々はちゃんと聴いていなかった…と思い知らせてくれたのが、ジャズ講座だった。
スイングジャーナルやダウンビート、どのジャズ雑誌でも星5つ、ガンサー・シュラーや、ラルフ・グリースンなどの大先生は、歴史的名演と口をそろえて誉めちぎる。おまけに『主題的即興演奏に於けるソニー・ロリンズの挑戦』と題するシュラーのエッセイまでが、ジャズ批評を代表する歴史的名文と評価される結果になった。ジャズ・ファンとグルメは、星の数にはめっぽう弱い。しかし、絶賛されるが故に、真実が見逃されるということもある。

講座では、このアルバムには、『ずれ』や、テンポの『揺らぎ』、バース・チェンジのミスが潜むことを、実際の音源を聴きながら確認し、その瞬間のソニー・ロリンズを始めとする各メンバーの心象風景まで、実際のプレイを聴きながら解き明かしていく。寺井尚之特製の進行表があれば、耳の肥えたプレイヤーでなくとも、自分達が今、この瞬間、曲のどの位置を聴いているのかが一目瞭然に判る。だから、寺井尚之と同じ目線で、演奏に現れる色んなシーンを一緒に楽しめるのです。
中でも圧巻は、“ストロード・ロードの謎”と呼ばれるバース・チェンジの謎解き。
ソニー・ロリンズのオリジナル、Strode Rodeは、ロリンズがシカゴ時代によく出演していたクラブ、ストロード・ラウンジにちなんだ曲で、講座以降、寺井尚之のレパートリーにもなり、ピアノトリオで楽しんでます。
AABA形式のテーマは12+12+4+12と、少し変則になっている。寺井は、この録音から、ハーモニーが余り明確に伝わってこないことから、「メモ的な譜面をその場で渡して録音したのではないか…」と推測する。
ここでのロリンズ-ローチのバース・チェンジは、試しに私が何度数えても何コーラスやってるのかさっぱり判らない。寺井尚之は何故、皆が判らないのかを、進行表を出して教えてくれる。実は「演ってるほうも判らなくなっているからだ。」と。結局、一瞬失った流れを、うまくアジャストして元に戻した結果、歴史的名演となったのです。
バース・チェンジを迷子にさせた誘因はフラナガンがヒットさせたテンションのきつい一発のコードが原因だったことが明らかになっていく。サイドマンとして抜群の評価を受けているフラナガンが、確信犯的に「判らなくなるようなタイミング」のバッキング・コードを絶妙に入れたのだ。
地道に仕事をする脇役フラナガン、メトロノームの様に正確無比なマックス・ローチ…ジャズ評論でお決まりのように出てくるキャッチフレーズが、講座ではどんどん崩されていきます。
その経緯は、推理小説を読むようで、知的満足度たっぷり!『間違い探し』にありがちなセコいところがない。詳しいことは、講座の本第一巻をぜひとも読んでいただきたいと思います。
夭折の天才ベーシスト、ダグ・ワトキンスはデトロイトの名門高専カス・テック出身、この学校の当時の音楽カリキュラムは並みの音大よりずっとハイレベル、教師陣はヨーロッパから亡命してきた一級のコンサート・アーティストが多かった。ダグはポール・チェンバースの従兄弟で一年間デトロイトで同居し、非常に仲良しだったと言う。晩年トミーのレギュラーだったピーター・ワシントン(b)にはダグの大きな影響を感じます。
進行表を見ながら、フラナガンのヒットさせたキツいコードを自分の耳で確かめて、「ほんまや、これはわからんようになるわ。」と納得、あれあれ、ほんとだ。ダグ・ワトキンスの逡巡するビートや、ローチのドラムから送られるサインに戸惑うロリンズ、今度はロリンズをフォローして、カチンと歯車のかみ合うバッキングを送るフラナガン、皆のプレイに、字幕がついたように良く判ったし、このアルバムを一層楽しめることが出来るようになりました。
フラナガンが、現場での「何か」にカッとしてガツンと押した『怒りの刻印』…でも、それは音楽を台無しにするどころか、却って、レイジーな浮揚感と、即興演奏に命を賭ける集中力との激しいせめぎ合いを生み、化学作用を引き起こしたのではないだろうか?
 マックス・ローチが牽引した二つの大車輪クリフォード・ブラウン(tp)とソニー・ロリンズ。
マックス・ローチが牽引した二つの大車輪クリフォード・ブラウン(tp)とソニー・ロリンズ。
ブラウニーは奇しくもこの作品が生まれた4日後に悲劇的な事故死を遂げた。
色々な書物に遺されたトミー・フラナガンの発言を読むと、この名盤の謎解き講座に陰影が付き、一層興味深いのです。
NY的なるジャズについて:
デトロイトから出てきた当時、NYのミュージシャン達は余りにもバド・パウエルとチャーリー・パーカーに、耽溺しすぎているように思えた。勿論、我々だって(デトロイトのピアニスト)パーカーやパウエルは好きだったが、我々にはもっと何か他のものがあると思っていた。例えば、NY派のドライブ感と同時に、我々にはもっとリリカルな要素があると。趣味の良さと、テクニックももう少しあると自負していた。まあ、それは私個人の意見だから間違っているかもしれないがね。
Jazz Spoken here/ Waine Enstice & Paul Rubin, 1992
“サクソフォン・コロッサス”参加の経緯について
偶然!偶然だったんだ。大勢のミュージシャンがプレステッジで録音していて、僕も名簿に載っていただけだったんだ。振り返ってみると、その頃に録ったものが全て今は古典になっている。参加していたのは幸運だった。ソニーとはバンガードで何回か共演したがツアーに同行したりするというようなことはなかった。
Downbeat誌 ’82 7月号
サキソフォン・コロッサスについて
現在のレコード製作では、気にいらないところは編集してしまうが、昔の録音は、ミスも何もかもそのままだ。だが、私はその方が好きだな。…“サキソフォン・コロッサス”の収録曲がエクサイティングだったどうかは知らないが、なによりロリンズと共演することが私にはエクサイティングだった。何故ならコールマン・ホーキンスを別にすれば、ロリンズは私が当時最も好きだったサックス奏者だったから。
Jazz Spoken here/ Waine Enstice & Paul Rubin, 1992
まあ、ロリンズはあれほど素晴らしいミュージシャンなのだから、<ブルー・セブン>が絶賛されたこと位どうってことはない。 実際の彼はあれよりずっと良いよ。
Jazz Spoken here/ Waine Enstice & Paul Rubin, 1992
ソニー・ロリンズについて
ロリンズはフラナガンにとって、いつもお気に入りのミュージシャンであり、”優しいスイートな男”だ。ロリンズは、スターであるプレッシャーに打ち勝つために、わざと近寄りがたい人物像を演じているのだとフラナガンは言う。フラナガンがロリンズと初めて出会ったのはデトロイト時代で、かの有名なローチ-ブラウン・クインテットが町に来た時だ。
“ロリンズは自分自身をどれくらい面白いと知っているのだろう?”という質問に、フラナガンはこう答えた 。
「彼は真剣そのものなんだけど、真剣なところがおかしいんだ。意識的におかしくプレイしようとしてるかどうかは知らない。でも僕にはおかしく聞こえてしまう。例えば“If Ever I Would Leave You” 初めて聴いた時には、もう床にぶっ倒れる程笑いこけたよ。だが、同時に、彼は真剣そのものだとも思えた。彼はあのスタイルでなくとも、色々なやり方でプレイできるんだ。しかし、その時は、彼のルーツである西インド諸島風に演ってるとは、知らなかった。凄く細かいビブラートで、殆ど初心者のような音色だよ。全く音にならないようなところまでホーンをオーバー・ブロウさせてね。でも、あのようなアプローチで、あれほど音楽的に出来る演奏家を私は他に知らない。」
Jazz Lives/Michel Ullman New Republic Books, 1977
“サキソフォン・コロッサス”の緊張感に満ちた名演は、天才音楽家集団を生んだ二つの街、ハーレム・ストリーツとデトロイトとのせめぎあいで実った果実なのかも知れない。
“サックスの巨人”の初期の代表作、やっぱりBGMとして流すのでなく、こっちも正座して真剣に聴きます!
CU

 《元カレ from Songbook》
《元カレ from Songbook》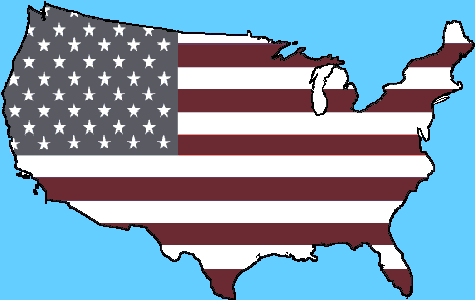 《彼氏 in U.S.A》
《彼氏 in U.S.A》
 《彼氏 in UK》
《彼氏 in UK》