 無声映画の大美男スター、ルドルフ・ヴァレンティノで大当たりした「キャラヴァン」映画、“熱砂の舞”
無声映画の大美男スター、ルドルフ・ヴァレンティノで大当たりした「キャラヴァン」映画、“熱砂の舞”
<キャラバン>は、寺井尚之の隠れた18番、ピアノとドラムのスリリングな掛け合いから、あのテーマが始まると、いつもお客様は大喜び!
今月のジャズ講座では、トミー・フラナガン3の傑作アルバム『トーキョー・リサイタル(A Day in Tokyo)』の<キャラバン>が聴けた。キーター・ベッツ(b)の地響き立てて唸るようなビートと、ギラギラ光ってズバズバ時空を切る、黒澤映画のチャンバラみたいな、ボビー・ダーハム(ds)のスティックさばき、トミー・フラナガンが二人の持ち味を生かし、息を呑むようなトラックだった。
来月のジャズ講座では、このアルバムから5ヶ月後、モントルー・ジャズ・フェスティヴァルで同じトリオをバックにエラ・フィッツジェラルドが歌う<キャラバン>が次回のジャズ講座で聴けます。
モントルーはスイス、レマン湖畔の高級リゾート、このジャズ・フェスは当時カジノの中で行われていたのです。
後で付いた歌詞は、砂漠を行く愛と冒険の旅路、レマン湖でヴァカンスやつかの間のロマンスを楽しむお客様にぴったり!下はエラが歌った1コーラス目です。
|
Night And stars above that shine so bright, The mystery of their fading light, That shines upon our caravan. Sleep Upon my shoulder as we creep Across the sand so I may keep This mistery of our caravan. You are so exciting, This is so inviting, Resting in my arms As I thrill to the magic charm of you With me here beneath the blue My dream of love is coming true Within our desert caravan… |
夜の砂漠、 輝く満天の星、 流れて消える神秘の流星は、 キャラバンに降り落ちる。 私に肩にもたれて、 眠っておいで。 砂漠を進む、キャラバンの 長き旅路に、 愛の魔法から醒めぬよう。 ときめく心、 わが腕に休む君、 君の妖しい魅力に囚われる。 空の下、君と寄り添い、 恋の夢は叶う、 愛の砂漠、二人のキャラバン… |
星降る夜空、砂漠の海、静かに進むキャラバン隊…異国の地に繰り広げられる愛と冒険のスペクタクル!歌詞のムードは、第一次大戦後に大流行したルドルフ・ヴァレンチノのサイレント映画(上の写真!)や、後に「アラビアのロレンス」として日本でも有名になった、砂漠の英雄、T.E. ローレンスの実話などの「砂漠ブーム」を強く意識したものです。
実際の作曲者、フアン・ティゾールは、エリントン楽団のバルブ・トロンボーン奏者です。20歳の時、プエルトリコから第一次大戦後の好景気に沸く本土に渡って来た。それは、はラジオがやっと出来た頃、間違ってもTVなんかない! 当時、庶民の娯楽は、劇場に行って、サイレント映画と“実演”つまりバンド演奏やショーを楽しむことくらい。劇場のピットOrch.の楽員がとにかく足りなかった時代。
プエルトリコは、本土よりずっとハイレベルの音楽教育で知られ、即戦力で使える音楽家の宝庫だった。だから、大勢のプエルトリカンがスカウトされてやって来た。ティゾールもその一人です。彼も劇場映画館のオーケストラ・ピットで、ヴァレンチノが砂漠の首長(シーク)として活躍する大スペクタクル映画、「血と砂」や「熱砂の舞」に女性達が失神するほどうっとりするのを観ていたに違いない。
 フアン・ティゾール(1900-84)
フアン・ティゾール(1900-84)
ティゾールは、<キャラバン>(’36)の他にも<パーディド>など、楽団の為にたくさん作曲している。エリントンやストレイホーンだけでなく、こういう作品を総括したのがエリントニアなんです。
’29年に入団し、15年間在籍した後、ハリー・ジェームズ楽団に破格の報酬で引き抜かれましたが、’51年、ジョニー・ホッジス(as)達、主力メンバーがドドっと退団した楽団の危機に、助っ人として再加入した。
楽団での彼の役割は、アドリブで魅了するソロイストではなく、しっかりとしたテクニックでエリントン・サウンドを支える縁の下の力持ち。ヴァイオリン、ピアノetc…あらゆる楽器に習熟していたから全体を考えプレイした。
勿論バルブ・トロンボーンでは、どんなに速く広く音符が飛び回るパッセージでも容易く吹ける名手であったから、エリントンは彼の為に、普通のスライド・トロンボーンでは到底演奏不能なパートを書きまくった。そんなティゾールの複雑なラインとサックス陣のとのコントラストが、随一無比のエリントン・サウンドを生んだのです。
ティゾールの長所はそれだけではありません。「規律」という楽団にとって最も大切なものを守った。本番でもリハーサルでも、仕事場に、誰よりも早く入ってスタンバイしている人だった。アメリカの一流ジャズメンは、日本よりずっと体育会系で、ファーストネームで呼び合っていても、上下関係が凄いのです。先輩が早く入っていたら、いくら「飲む=打つ=買う」三拍子揃ったバンドマンでも、おいそれ遅刻など出来ません。こういうメンバーがいると、バンマスはどんなに楽でしょうか!
故に、ティゾールはエリントンの代わりにコンサート・マスターとして、リハーサルを仕切るほど重用されました。ですからずっと後から来て側近となったビリー・ストレイホーンと確執があったのは、むしろ当然のことですよね!
<キャラバン>のエキゾチックなサウンドは、サハラ砂漠ではなく、西インド諸島で生まれたフアン・ティゾールのものだった! エリントンは『ビバップとは、ジャズの西インド的な解釈である。』と言っている。
この作品にも、ビバップを予見するように、オルタードと呼ばれるスケールが多用されています。
それは、ティゾールをエリントンに結びつけた第一次大戦から、社会の変化につれて、ビバップへと連なって行く。
その道筋もまたInterludeにとっては、愛と冒険の一大スペクタクル!
次回のジャズ講座は6月14日(土)、ジャズ講座の本第5巻も新発売!
CU








 エリントンやストレイホーンを知らない人も、このアルバムは一度聴いてみて欲しい!
エリントンやストレイホーンを知らない人も、このアルバムは一度聴いてみて欲しい!  左:デューク・エリントン、右:ビリー・ストレイホーン
左:デューク・エリントン、右:ビリー・ストレイホーン 













 マックス・ローチが牽引した二つの大車輪クリフォード・ブラウン(tp)とソニー・ロリンズ。
マックス・ローチが牽引した二つの大車輪クリフォード・ブラウン(tp)とソニー・ロリンズ。
 《元カレ from Songbook》
《元カレ from Songbook》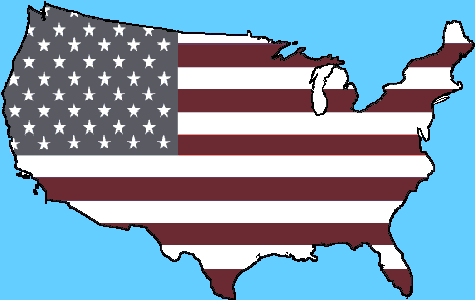 《彼氏 in U.S.A》
《彼氏 in U.S.A》
 《彼氏 in UK》
《彼氏 in UK》